あなたは今、「自分の好みにぴったりのコーヒーを、自宅で焙煎して淹れてみたい」と思っていませんか?
でも、いざ始めようとすると…
- 焙煎方法が多すぎて迷う
- 器具選びで手が止まる
- 焙煎度って何?と混乱する そんな状況になっていませんか?
本記事では、初めて自家焙煎に挑戦する人でもわかりやすいように、必要な知識と具体的なステップを丁寧にまとめました。
この記事を読めば、「とりあえずやってみよう」が「これならできそう!」に変わるはずです。
焙煎とは?初心者でもできるコーヒーの楽しみ方

焙煎とは、コーヒーの生豆(青くて硬い状態)を加熱して、香ばしい茶色い豆に仕上げる工程のことです。
焙煎によって、豆の中にある糖や酸が変化し、風味・香り・コクが生まれます。
初心者の方でも、家庭にある道具を使ってスタートできるので早速チャレンジしてみましょう。
火加減や焙煎時間に注意すれば、失敗も少なくできるでしょう。
自家焙煎のメリットとデメリット
メリット
- 新鮮なコーヒーが飲める 焙煎直後のコーヒーは市販品に比べはるかに香ばしく、その中に甘い香りを含みます。 コーヒーを袋から出した瞬間からその香りがあなたを包み、特別な時間をもたらしてくれることでしょう。
- 味の調整が自由 自分の好みを理解していても購入した商品が思ったものと違ったという経験をお持ちの方も多いはず。 この点、自家焙煎ができればほんの少しの調整ができるようになるので自分の好みまで合わせることができるようになります。 また、新たな味わいへのチャレンジができることも自家焙煎の強みです。
- 愛着が湧く コーヒーを淹れて飲む体験だけでなく焙煎の体験までできるので、より一層の充実感を得られます。 コーヒー作りのプロセスを深く理解することにもつながり楽しむことができます。 また、家族や友人にふるまうことで特別な体験を提供することができるでしょう。
デメリット
- 失敗する可能性あり 焙煎時間や火力の調整が必要なので失敗の可能性はあります。期待した焙煎度にならないこともあるので何度か試行錯誤が必要になることがあります。
- 手間がかかる 焙煎後にはチャフ(皮)と呼ばれるものの処理があります。チャフとはコーヒー豆をおおっている薄い皮のことですが、焙煎後に剥がれコーヒー豆と分離されるのですぐに処理していく必要があります。また、焙煎中の煙の処理も必要になるので全体的に手間がかかってしまいます。
- 初期投資が必要 焙煎事態は家庭にある器具でものできるのですが、コーヒーを淹れるのも初めての方はグラインダーや、計量器、抽出器具なども必要になり、費用がかかってしまいます。
初心者にとっては、この“手間”が最初のハードル。でも、正しいステップで始めれば乗り越えられます。
焙煎の方法:まずはここから選ぼう
自宅でできる焙煎方法には、いくつか選択肢があります。
フライパン
安価で手軽。少量のコーヒー豆を焙煎するならこれで十分。
フライ返しなどを使って豆を混ぜながら焙煎していきます。
手鍋
フライパンと同様のメリット。さらに蓋がついていることで温度を保ちやすくなります。
温度が保ちやすいと焙煎時間が安定するので作りたい焙煎度の再現性が上がります。
鍋の蓋はガラス製だと中の状態が観察できるのでさらに良いです。
手網
焙煎した時の香りがわかりやすいことがメリットですが、火加減が難しく、他の焙煎方法に比べ煙が多いということがデメリットです。
家庭用焙煎機
全自動で焙煎を行なっていくれるので何も気にすることなく気軽に焙煎できます。
ただし価格は高めで導入コストが問題になるでしょう。
おすすめは手鍋
最初は手鍋から始めるのが簡単です。上でも触れましたが鍋の中の温度を保ち、調整も行うことができるので、他の方法に比べ私は焙煎しやすいと感じました。
大まかな焙煎度合い
焙煎度によって、同じ豆でも味がガラッと変わります。
本来は細かく分類されているものですが、大まかな焙煎度と特徴は下記の通り。
| 焙煎度 | 風味の特徴 | 色 |
|---|---|---|
| 浅煎り(ライトロースト) | 酸味が強く、華やか | 明るい茶色 |
| 中煎り(ミディアムロースト) | 甘味と酸味のバランス | 中間的な茶色 |
| 深煎り(フレンチロースト) | 苦味・コクが強く、ビター | 黒に近い |
実際の焙煎ステップ:失敗しないための流れ
ここからは私が行っている手鍋での焙煎の手順を公開します。私が焙煎する中で得た気づきも共有したいと思いますので参考にしてみてください。
また、焙煎中は煙と強いコーヒーの香りが発生します。必ず換気扇を回すか換気のできる環境で行いましょう。
集合住宅の場合は近隣への配慮も必要です。最初は少量で試し、状況を確認しながら始めた方が無難かもしれません。
Step1|道具の準備
- 手鍋
- カセットコンロ
- ザル(プラスチックでないもの)
- うちわ(冷却用)
以上が焙煎に必要な最低限の道具です。
焙煎直後の豆は高温になっていますのでプラスチック製のザルは変形することがありますので注意してください。
その他あると便利なもの
- タイマー:コーヒー豆の焙煎が始まってから煎り上げまでを計測しておくと、次回の参考になり焙煎の安定化につながります。
- 重量計(クッキングスケール):生豆の重量を測ります。前回との比較をする際に重量が違うと単純に比較しにくくなるので重量計があると便利です。
Step2|生豆の準備
- 生豆の購入
- ネット通販(Amazonや楽天など)
- コーヒー専門店
- 焙煎所や業用食材店
- 欠点豆を取り除く
※欠点豆とは:簡単に言えば普通の状態ではない豆のこと。豆の欠けや虫食いがあればコーヒーの味に影響が出るので取り除いてしまいましょう。
Step3|予熱
- 鍋の予熱スタート
- 目安は手をかざして熱いなと思うくらい
予熱はしっかりと行います。過去の経験から、鍋が十分に熱くなってから焙煎すると気温などの影響を受けにくく、安定した仕上がりになることが分かりました。
Step4|加熱(焙煎スタート)
- 中火〜強火でスタート
- 5秒に1回程度鍋を振る
- 最初は水分が飛んで「シュー」という音がする
- 生豆の香り〜少し甘い香りに変化する
- 豆の色は薄い緑→黄色
最初は豆に含まれる水分が飛んでいく過程です。上記のような色合いと香りの変化が起こります。
焙煎ムラがないように定期的に鍋を振って混ぜるのがコツです。
Step5|1ハゼを確認(加熱開始から約7分)
※1ハゼとは:豆の中の水分が蒸発するときなる小さな破裂音のこと。
- 「パチパチ」とポップコーンのような音
- この段階からコーヒーらしい香りになってくる
- 豆の色は黄味を帯びた茶色→明るい茶色
いよいよコーヒーを焙煎している感が強くなってきます。1ハゼの音は意外と小さいと感じたことがありますので良く耳をすましておきましょう。
1ハゼが終わるあたりから鍋の蓋を開けたり閉めたりしてみてください。そのままの状態だと温度が高すぎ、焙煎が早く進みすぎてしまいます。
また、出来上がったコーヒー豆に燻されたような香りがついてしまうこともあるので適度な排煙が必要になります。
Step6|焙煎終了タイミングを決定
- 浅煎り:1ハゼ直後に止める
- 中煎り:1ハゼ終わり〜2ハゼの手前
- 深煎り:2ハゼが始まってから止める
※2ハゼとは:豆の中のガスが増え豆が膨張したときに出る音。
任意の焙煎度合いで焙煎を終了しましょう。
Step7|すばやく冷却
- ザルに移し、うちわで扇ぐ
- チャフをしっかり取り除く
※チャフとは:生豆を覆っている薄い皮(シルバースキン)が取れたもの
うちわで仰ぐ過程でチャフが舞い散ります。また、チャフは火がつきやすので火事には十分注意しましょう。
焙煎を成功させるコツ
- 焙煎記録を取る 焙煎記録をとると次回以降の参考になります。細かくとる必要は最初の時点では必要ないです。焙煎開始から1ハゼまでの時間と終了時間がわかれば十分参考になります。
- 一度に少量で試す 最初は100g程度から始めるのがいいです。焙煎機の容量にもよりますが手鍋の場合は大体このぐらいが扱いやすいと感じました。
- 明るい場所で観察 ハゼのタイミングは音でわかりますが、コーヒー豆の色も参考になります。そのために焙煎環境は明るくしておきましょう。
- 冷却をしっかり行う 冷却は素早く行います。 ザルに移した後も予熱で焙煎が進んでしまうので、好みの焙煎度で終わらせるためには素早い冷却が必要になります。
豆の保存方法と飲み頃:美味しさを保つためのコツ
保存容器:密閉容器+冷暗所がベスト(冷蔵庫はNG)
焙煎したてのコーヒー豆はとてもデリケートで、空気や光、湿気によって風味がどんどん劣化してしまいます。そのため、保存にはしっかりと密閉できる容器が不可欠です。遮光性があり、外気との接触を最小限に抑えられるものがおすすめです。
保存場所は、直射日光の当たらない冷暗所が理想的。特にキッチン周りは温度が変化しやすいため、棚の奥や食器棚の中など、できるだけ温度と湿度が安定した場所を選びましょう。
「冷蔵庫保存」は一見よさそうに思えますが、豆が湿気を吸いやすくなるため実はNG。頻繁に出し入れすることで結露が起こり、劣化を早めてしまう恐れもあります。
ガス抜き期間:焙煎後1〜3日置くと味が安定
焙煎直後の豆は、まだ内部に二酸化炭素が多く残っており、そのまま使うとお湯を注いだときにガスのせいでうまく抽出できないことがあります。いわゆる“ガス抜き”の期間を1〜3日ほど置くことで、豆の中のガスが自然に抜け、抽出の安定性や味のバランスが整ってきます。
急いで飲むよりも、少し待つ楽しみも含めて自家焙煎ならではの楽しさです。
飲み頃の目安:焙煎後3〜7日が香りのピーク
コーヒー豆は焙煎後、日ごとに風味が変化していきます。とくに香りのピークを迎えるのは、焙煎後3〜7日ほど。このタイミングでは、ガスが落ち着き、豆本来の甘さや香ばしさが引き立ち、もっとも香り高く、まろやかな味わいを楽しむことができます。
豆の種類や焙煎度によって多少の違いはありますが、「香りを楽しみたい」「豆の個性を感じたい」という方には、この時期に淹れるのがおすすめです。
ちなみに、浅煎りほどピークが早く、深煎りほど少し遅くなる傾向があります。毎日少しずつ飲んで、味の変化を感じながら飲み頃を探すのも、自家焙煎の醍醐味のひとつです。
よくある質問
Q1. 失敗したらどうすればいいですか?
少量で練習して記録を取りましょう。「どう失敗したか」が最大のヒントになります。その記録を参考に火力や時間を変化させてみましょう。
Q2. 音が聞こえないときはどうする?
焙煎量が少ないと音が小さい場合があります。色や香りの変化にも注目しましょう。
Q3. 煙がすごくて心配…
換気扇+窓+サーキュレーターを併用すれば対策できます。心配な方は近隣の方へ配慮しながらベランダ焙煎も検討してみてください。
自分で焙煎するからこそ、味わえる世界がある
最初はうまくいかなくても、「この豆はどう変わるんだろう?」とワクワクしながら焙煎してみてください。温度、時間、保存…一つひとつの要素が、あなたの味を作っていきます。
理想の味に近づけたときの達成感は、何物にも代えがたい体験になるはずです。
まとめ
- 焙煎はコーヒーの風味を決める重要な工程
- 手間はかかるが、再現性と知識があれば失敗は減らせる
- 最初の一歩は、「簡単な器具」+「少量」から
自宅焙煎は、単なる“淹れる”以上の楽しさがあります。
一杯のコーヒーから、あなたの新しい日常が始まるかもしれません。






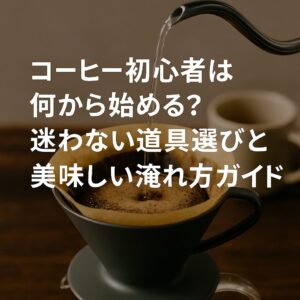
コメント